はじめに
「工業高校ってどんな学校?普通科とどう違うの?」「進路は?」そんな疑問を持っている中学生や保護者の方に向けて、
私は偏差値40ほどの工業高校の電気科に通い、資格を取得したり生徒会に入ってみたり、ほどほどに真面目に勉強しながら、青春を楽しもうとした高校生活を過ごしました。現在は進学して、また電気科で学び続けています。
この記事では、そうした私の体験をもとに、工業高校の電気科の授業や進路、生活の雰囲気をできる限りわかりやすくお伝えします。
目次
進路について
私の学年は55人中、10人程度が専門学校や私立大学に進学しました。残りは就職です。
就職先は、大企業の工場、地元の造船所、郵便局、発電所などさまざまですが、おおよそ8割は工場勤務になります。
大企業ほど残業が少なく、犯罪などを起こさない限り解雇されることもないそうです(これは私が高校2年生の冬休みにインターンに行った三菱の工場の方から聞いた話です)。
工業高校の授業構成(3年間)
| 科目分類 | 概要 | 合計単位の目安 |
|---|---|---|
| 一般教科 | 国語・数学・英語・理科・社会・保健体育など | 約30〜35単位 |
| 専門科目 | 工業技術に関する座学・実習 | 約30〜40単位 |
| 選択科目 | 学校やコースによって自由に設けられる授業 | 数単位(+α) |
- 1単位=週1時間 × 35週=35時間
- 専門科目が30〜40単位なら、1,000〜1,400時間近くを専門に使う計算になります。
1年生の授業と実習
私の高校では、2年生から電気科・機械科に分かれるため、1年生ではどちらも同じ授業を受けます。私は2年から電気科を選びました。
1年生の時点から週に2時間の実習があり、溶接・電気工事・旋盤の作業を経験しました。これは学校の設備によって異なると思いますが、 私たちの代では、地元の造船所を定年退職されたベテランのおじいちゃん先生が実習を教えてくれました。
専門座学と資格取得
1〜2年生では、基本的に資格取得を目指した授業が中心です。内容はそこまで難しくなく、1年生では漢検3級やそれに相当するレベルの資格を3つ程度取得するのが一般的でした。
他にも製図や電気基礎といった、直接資格にはつながらないが技術者として必要な基礎を学ぶ授業もあります。
名前は堅いですが、実際は「美術っぽい製図」や「オームの法則しか使わない理科」といった感覚で受けていました。
3年生からは就職対策
3年生になると、就職を見据えた授業が増えます。 具体的には、就職試験対策の筆記練習、敬語の使い方、面接のマナーなどを授業で学びます。 夏休みにも登校日があり、面接練習や履歴書の添削を受けることもありました。
ただ、進学希望の普通科の生徒も夏に補習があるので、そこは工業高校と大きくは変わらないと思います。
男女比
工業というのは力仕事や鉄とかオイルとか作業着とかの可愛い要素がないので男女比が偏ります、うちの代は比較的女子が多い方でした70:3でしたこれは歴史的快挙です、毎年一人も来ないのが普通でこの三人が来るまで三年間いなかったらしいです、とても貴重な存在です、彼女たちはとてもワイルドでした。
治安、民度
一年生で授業中にねるねるねるね作って食うやつがいました、二年生で喧嘩が二回起きました、三年生の先輩はベランダに出てパンツ一丁で野球拳に負けていました。男しかいないので治安は悪いです、毎週柔道の授業をしていたのもあるのですが、取っ組み合いが大好きで、つかみあいしてじゃれて座るときも座ってる人の上に乗ります。ほとんどの人は女の子が好きなので安心していていいです。
まとめ
- 高校卒業して就職したい人
- いろんな作業を体験してみたい人
- 将来的に工業に携わりたい人
- 自由に時間を使いたい人
- 男が好きな人
以上の人におすすめです、自分はこの道を選んで人生にほかの人とは違った味が出たような気がするので良かったと思います。

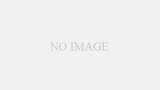
コメント